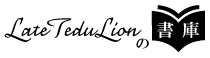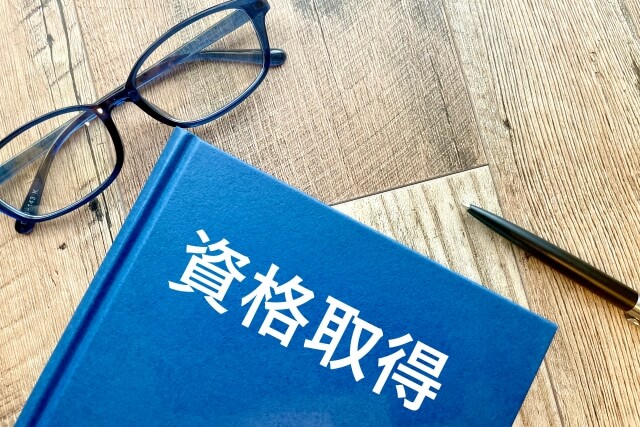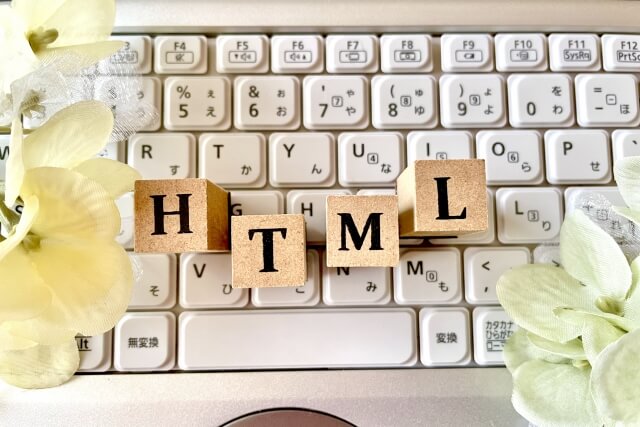工事現場や解体現場では、作業場がシートで覆われて中が見えないことがあると思います。工事現場や解体現場の足場を覆っているのは防音シートで、工事音や解体音が近隣に漏れないようにする役割があります。 本記事では、工事現場の足場 […]
大根の葉を乾燥させたものを「干葉(ひば)」と呼ぶそうです。入浴剤として用いられているようで、身体をよくあたためることから冷え性、腰痛、肩こり、神経痛などに効果があるなどとされているようです。辛い腰痛や肩こり、冷え性などで […]
日本近海の太平洋で発生する大地震は薬100年単位で発生しているとも考えられているようです。海底のプレートのズレから、そのような大地震の予測が行われているうですが、歴史のなかでおおよそ100年間のスパンをもって繰り返される […]
水彩画をはじめたばかりの皆さんへのアドバイスとして、絵の具をまぜる際に、必要以上の色彩を混合させないことです。水彩画は透明感が命でもあり、透明感を保つには3色以上の色合いを混色しないルールを保つことです。明るさを調節した […]
1950年代後半、農産物を包装する資材として新たに登場したのが段ボールとされています。 現在ではそこかしこで便利に利用されている段ボールですが、それまで製造はされていたものの、農産物の包装という観点での使用はなかったと言 […]
高齢者にとって健康な「歯」の本数は、健康寿命を表すなどという研究者たちもいるようです。近年の研究によって皆さんが食事の際に行う「咀嚼」が、人間の健康寿命に大変重要な働きをしていることが分かりつつあるようです。もちろん「咀 […]
税理士試験の実施日程等について、令和2年度(2020年度)を例にご紹介しておきましょう。 試験申込用紙の交付(4月16日~5月19日)、受験申込受付(5月7日~5月19日で受験地を管轄する国税局等への「一般書留」、「簡易 […]
最近は、生き残りをかけた飲食店のオーナー達が、お店の経営を模索する中で、様々な試みが行われているようです。 グルメ研究家などが、そのような飲食店の経営に悩みを持つオーナーたちに語りかけていることは、お店側の演出する「ワク […]
「アヒル」は、人々が、野性の「マガモ」を食用として飼っていたものだと言われています。 その「アヒル」と「マガモ」を掛け合わせ人工交配させた種が、「アイガモ」で、あるのだそうです。 「カモ」は、奈良時代から「鴨汁」などとし […]
現在、Webサイト制作においてが注目を浴びています。WordPressとはどのようなものか紹介していきます。 ・Webサイトとホームページ 日常会話において「Webサイト」と「ホームページ」は同じ意味で使われがちですが、 […]